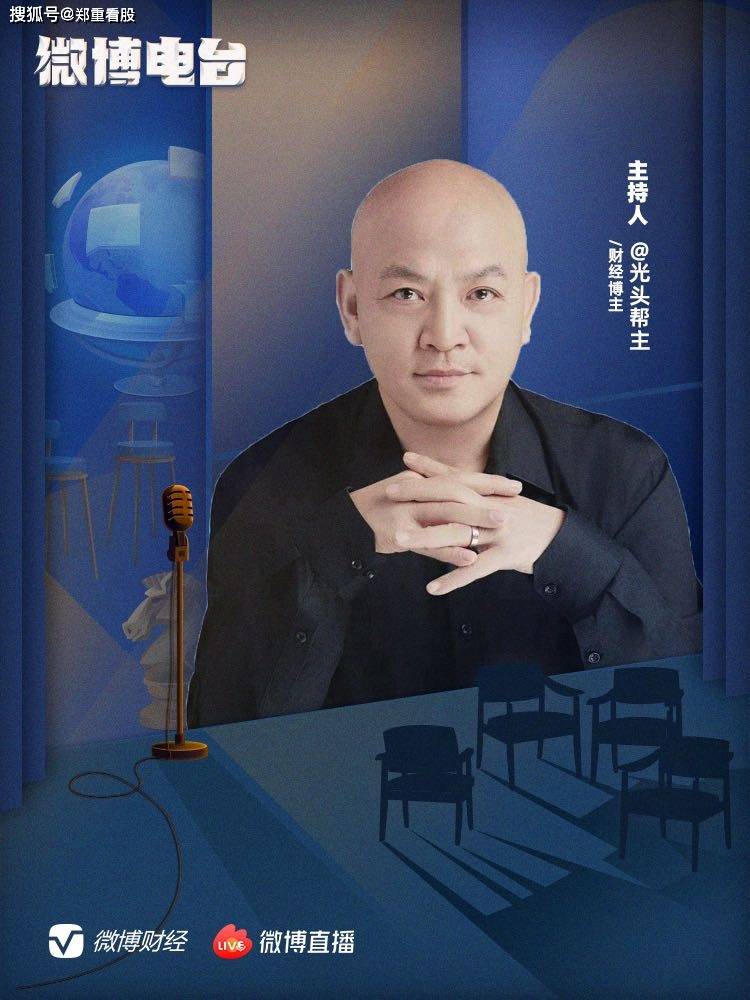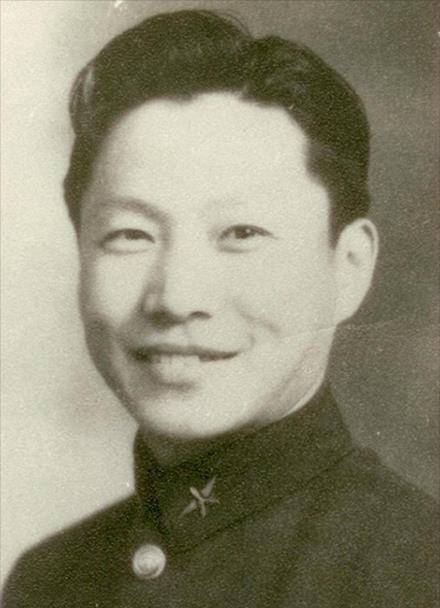かつて中国領土だった国々が、混乱に乗じて独立。しかし、その後の運命は…?中国周辺の、かつて我々の領土だった国々の今を覗いてみましょう。驚きの事実が満載です!

まず一つ目はモンゴル。20世紀初頭から独立の兆しを見せ、1920年代に独立を果たしました。背景には、領土欲の強いロシアの存在が。中露間の緩衝地帯を築きたいロシアの思惑と合致したのです。
しかし、独立後のモンゴルは、砂漠地帯という環境や科学技術の遅れなど、多くの困難に直面。内陸国であるため、貿易の窓口がなく、発展が阻害されています。ただ、中露という二大国の存在は、安全保障においては大きなメリットと言えるでしょう。

次はベトナム。秦の始皇帝が百越の地を支配下に置いた際、ベトナムも含まれていました。しかし、清朝の衰退とともに失われた土地です。ベトナムの発展は、ある将軍の決断によって左右されたと言われています。中越戦争後、撤退する際、許世友将軍は、インフラを徹底的に破壊したのです。これが、ベトナムの発展を遅らせた一因とされています。

そして、カザフスタンとタジキスタン。ソ連の一部だったというイメージが強いかもしれませんが、明朝時代にはカザフスタンが、漢朝時代にはタジキスタンが、中国の版図に入っていました。しかし、清朝時代にロシアに奪われてしまいました。両国もモンゴルと同様、内陸国であるため経済発展が遅れています。特にタジキスタンでは、人口の半数以上が貧困線付近で生活しています。
キルギススタンも、カザフスタン、タジキスタン、モンゴルと同様の状況です。内陸国であり、経済も低迷しています。最後に、トゥヴァ共和国。現在はロシアの一部ですが、かつては唐努乌梁海と呼ばれ、中国の領土でした。唐朝時代には堅昆都督府が設置され、管理されていましたが、清朝時代にロシアに奪われました。

清朝初期には、ロシア軍を圧倒することもできましたが、清末にはロシアの侵略を防ぐことができず、唐努乌梁海の支配権は揺らぎました。1990年代には、様々な要因から放棄せざるを得なくなり、ロシアに譲渡されました。しかし、ロシアは経済運営が得意ではなく、唐努乌梁海の人々の生活は苦しい状況が続いています。現在、一人当たりのGDPはわずか3,000ドル程度です。