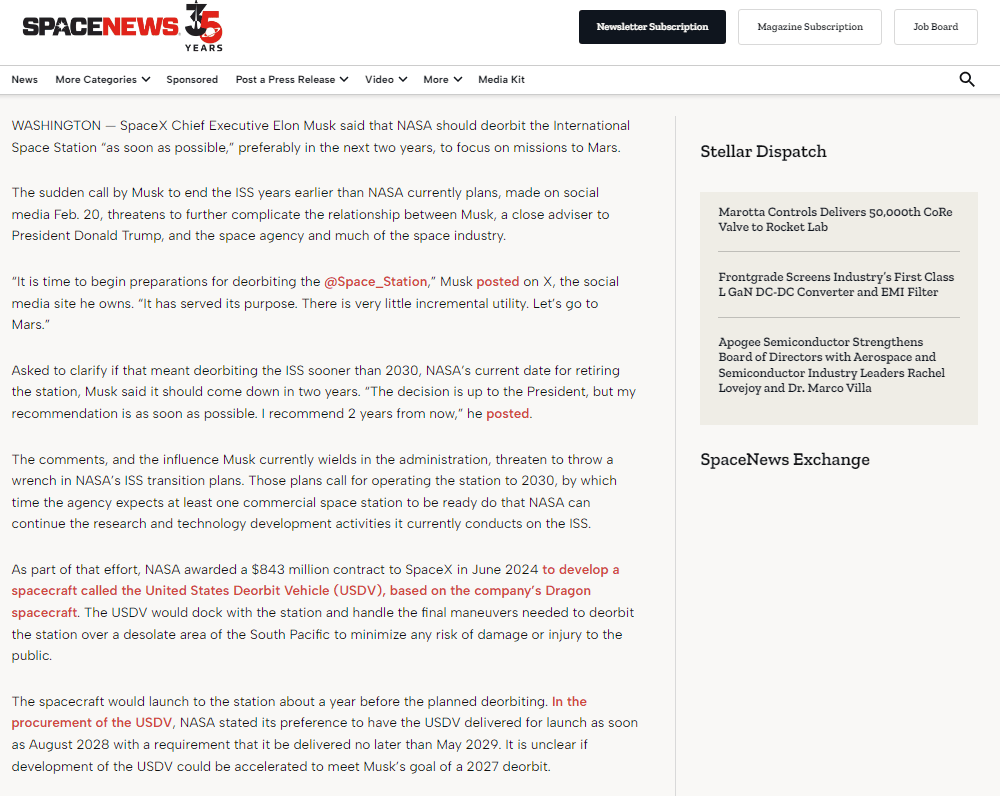1938年2月17日、新郷の城壁は日本軍によって占拠されました。政府機関、駅、製粉工場、住民の家々…すべてが日本軍に占領され、利用されました。わずかに残された史跡にも、侵略者の影が残されました。
その瞬間、文明は獣の爪で引き裂かれ、古物は血なまぐさい風に染められ、古の鄘の地は悲しげに色を変え、牧歌は消え去りました…

新郷の北城壁では、2人の日本兵が衛水を間近に見つめ、遠くの太行山を眺めながら、互いに意見を交わしています。
写真では、城壁はすでに破損していますが、北宋の政和元年(1111年)に邵博が出資して創建した石橋「邵公橋」(明朝の1497年から「民楽橋」と呼ばれる)が、依然としてはっきりと見えます。新郷で最も古い石橋として、衛河の南北両岸の住民を結ぶ唯一の通路であり、古人はそれを「鄘の咽喉の要地」と呼びました!
「(唐の618年)に土城が築かれ、衛水の陽に位置しました。中央が高く、四方が一丈八尺にそびえ立ち、覆われた釜のようで、陰陽家は『亀背城』と呼びました。門は四つあり、東は『迎恩』、西は『来賓』、南は『朝陽』、北は『拱辰』と呼ばれました。」
全住民の力によって、歴代の県令が主導し、「土城」は明の崇禎朝に「レンガ城」へと姿を変え、風雨にさらされ、民智が込められた新郷の城壁は、衛河のほとりに雄大にそびえ立つようになりました。
しかし1938年2月17日、この威厳に満ち、歴史のある城は、日本の侵略を防ぐことができませんでした。日本軍第十五聯隊は「民楽橋」から城壁に入りました…

様式の異なる軍帽をかぶった3人の日本兵が、「民楽橋」を背景に、1939年9月に衛河南岸で「記念写真」を撮影しました。その目的は、右端の新兵の到着を記念するためでした。
「民楽橋」の橋洞の最も高い場所は、すでに衛河の水に迫っており、新郷の「母なる川」である衛河が、この時、豊水期にあったことがわかります。また、裸の少年が写真に写っていることから、当時の新郷の気候はまだ耐え難いほど暑かったことがわかります。

1938年11月20日、日本軍第十四師団第二十七旅団旅団長の豊島房太郎少将は、関帝廟の前で馬に乗った戎装姿の写真を残しました。
関帝廟は、古代人が関羽(関羽の爵位は「漢寿亭侯」)を祀る場所であり、明の正徳時代の『新郷県志』には、「寿亭侯廟は崇化街(現在の東街)にあり、元の至元七年(1270年)に建てられた」と記されています。
時が流れ、歳月が過ぎ、梁思成、林徽因夫妻と共に、河南省各地の古建築を調査した中国营造学社メンバーの劉敦楨は、著書『河南省北部古建築調査記』の中で、「その年代は、元の至元年間に創建されたとしても、大部分が何度も修正されている」と慨嘆しました。
馬に乗った豊島房太郎は、1946年11月28日に自分が「虐殺への関与」などの罪で投獄され、『日本重要戦犯リスト』の第193位に名を連ねるという結末を迎えるとは、想像もしていなかったでしょう。

新郷県城が河南省第四行政督察区治署の駐屯地となったため、1933年に「(河南)省が2000元を投資し、豫北の14県が共同で1.72万元を集めて」建設されたオフィスビル(通称「工字楼」)が、新郷の人々の目に触れるようになりました。新郷、済源、温県、孟県など豫北の14県の重大な公務は、すべてここで審議され、裁定されました。
しかし、日本軍による新郷の占領に伴い、この政府オフィスビルは、新郷に駐屯した日本軍によって聯隊本部とその傀儡政府である「新郷県公署」のオフィスとして使用されるようになりました。
写真は1939年7月、日本軍第220聯隊聯隊長の見城五八郎大佐と一部の尉官が、オフィスビルの前で撮影したものです。

明朝の天啓三年(1623年)に建てられた郭淐「尚書牌坊」(別名「功徳坊」)は、城東定国村の郭氏一族の栄光であり、新郷城内外に残された数少ない明朝建築の至宝です。
この精巧なデザインで、高く雄大な牌坊は、新郷が陥落した7年以上の間、日本軍に非常に好まれ、一緒に写真を撮られることが多く、日本軍の宣伝部門が1939年から発行した「軍事郵便」(絵葉書)「新郷印象」にも何度も登場しました。

康熙四年(1665年)、明君康熙の時代を迎え、新郷の人文が盛んになった時、知県の王克儉は城壁の四隅に敵楼を再建すると同時に、「文楼を建てるのが良い」と考え、「巽の方角に楼を建てて文昌を祀り、『来雲』と名付けた」。「扶搖に乗って上るという意味である」。
その後、乾隆九年(1744年)に新郷知県の趙開元が「重光」と改名しましたが、民国十二年(1923年)に新郷県知事の韓邦孚が主導し、邑人の田芸生が主編した『新郷県続志』は、その元の名前を回復し、『続志・県城図説』で明確に図示しました。
1944年5月20日、「河南会戦」(別名「豫中会戦」、4月17日~6月19日)の進展を支援するため、日本軍第110師団輜重兵第110聯隊第四中隊は、河北省獲鹿を出発し、石門(現在の石家荘)、新郷、修武などを経由して洛陽に向かいました。
新郷で一時待機していた期間、尻当て帽をかぶり、軍刀を手に持った日本軍尉官が新郷の城壁で記念写真を撮りました。その背後にある四角錐の屋根構造を持つ、レンガ造りの2階建ての建物が「来雲楼」です。

1942年5月、白川拾仕という日本兵が、新郷城内のかなり規模の大きい民家で、バイオリンを弾いている写真を撮影しました。
写真をよく見ると、白川拾仕は14歳くらいで、明らかに少年兵です。これから、日本軍の兵源が深刻に不足していることがわかります。その最終的な結末は、すでに想像できるでしょう。

日本兵が衛河南岸に立って記念写真を撮りました。その背後には、新郷で2番目に南北の交通を便利にする「華北記念橋」と、「通豊製粉工場」の高い煙突がそびえ立っています。
日本軍が新郷に侵攻した後、かつて新郷の市場を豊かにし、南北に名を馳せた「通豊製粉工場」は、日本軍に占領され「河南軍管理第八工場」と改名されました。中村愛四郎(後に新郷日本居留民団会長)が工場長に就任し、100人以上の日本兵が工場の安全警備を担当しました。
現在、橋も工場も健在です。歴史の煙は今もそれらの周りに漂い、その体内に染み込んでおり、絶えず行き交う人々に過去のメッセージを伝えています。悲しみであれ喜びであれ、過去を記憶することでのみ、明日を迎えることができます。

姜庄大街と石榴園大街の交差点にある「鐘鼓楼」は、当時の新郷のランドマークでした。その建設年代は不明ですが、『新郷県続志』(1923年版)の刊行後であると考えられています。多くは、1933年から1935年に唐肯が河南省第四行政督察区専員兼新郷県県長を務めた時期に建造されたと考えています。
そこに刻まれた「時間を守る」と、四方の「惜陰」、「起舞」、「待旦」、「揮戈」は、中華文化を広めるとともに、「時間」- 新郷が陥落した7年以上の苦難の歳月を、新郷の人々の脳裏に刻み込みました。
交通の要所であり、特に楼の高さが目立つため、日本軍はしばしば掃討の後、ここ(日本軍は「時計台」と呼んだ)を集合場所として使用しました。

1939年4月11日、数十人の日本兵が六角亭の前で記念写真を撮りました。この時、日本軍第十四師団と第三十五師団が交代する準備をしていた時期であり、写真は第十四師団の一部兵士が新郷を離れる前の記念写真であるはずです。
六角亭は「暴張公園」内の建築物です。公園は、辛亥革命の烈士である暴式彬、張希聖を記念するために、1924年に河南を主政した胡景翼が辛亥革命の元老である于右任らと共に提唱して建設された公園です。
亭の西側、川を隔てて建っている建物は、1935年8月に竣工し、2年以上使用されている「河朔図書館」です。
日本軍の侵略占拠により、本来文明を伝え、授業を行い、疑問を解くべき図書館は、日本軍の「偕行社」(軍人クラブ)などの部署の駐屯地となり、厳粛で優雅な「暴張公園」も日本軍第一六八兵站病院(陸軍病院)となりました。この病院は、実際には日本軍甲第1855部隊「華北防疫給水部鄭州支部新郷出張所」、つまり生化学兵器の研究製作と人体実験の場所でした。
「羊頭を掲げて狗肉を売る」ため、ここの医師の多くは、「病院」の医師という名前を利用して、戦後「戦犯」として受けるべき処罰を逃れました。

明の万暦四十三年(1615年)に建てられた潞王朱翊鏐の陵墓は、中国で最も保存状態が良く、敷地面積が最大の明代の藩王の陵墓です。
朱翊鏐が新郷、衛輝などで行った行為を考慮して、人々は一貫して彼を「潞王墳」と呼んでいます。
1915年、日本の上海東亜同文書院第十三期生が新郷を調査した際、「潞藩佳城」の石牌坊の雄大さに深い印象を受け、「潞藩佳城」の石牌坊の写真を撮影し、『中国省別全志』の「新郷」の章に掲載し、「新郷県明朝潞王の墳墓」と説明しました。
日本軍が新郷を占領した後、「潞王墳」の真の姿を見ることができたため、潞王墳守備隊の4人の日本兵が「潞藩佳城」の石牌坊の前で絆創膏旗を持ってここに到着した証拠を残しました。旗を持っている人の身長は、劉秀が「倭」の字を使って思想を表現したのが正確であったことを証明できます。