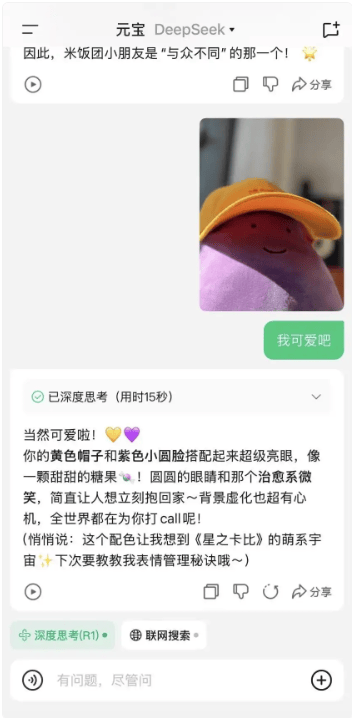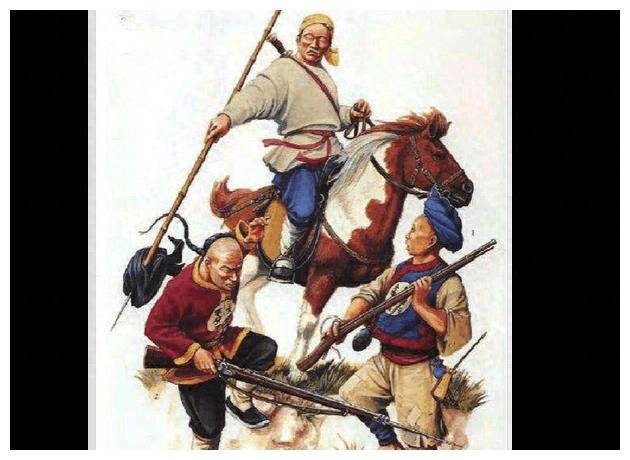1939年12月、第32軍第141師第723団は江西省靖安県城西郷間、九仙湯付近に駐屯していました。12月7日、部隊は白槎から修水を経て徳安県と永修県以西の磨西頭、抱桐地区へ、日本軍の後方で遊撃戦を行うよう命令を受けました。9日、団長の王啓明は部隊を率いて修水南岸に到着、魏家橋、王家嶺、大屋地区に分散し、修水を渡る準備をしました。

12月12日、第723団は修水河岸の偽軍、宋良臣部の秘密の協力のもと修水河を渡りました。同日、師長の唐永良も師部と直属部隊を率いて修河を渡り、万家嶺西北部地区に到着しました。14日、唐永良師長は警衛連を率いて雷鳴鼓劉、背溪街、張鼓山を経て抱桐付近の第723団駐屯地を視察し、部隊指導を行いました。
16日午前、王啓明団長は警衛連を率いて唐師長と共に万家嶺戦場へ状況視察に向かいました。午前7時半頃、彼らは抱桐を出発し、河橋を経てまず張鼓山に到着。山麓には数軒の農家があり、王啓明は金銭で農民を雇い、唐永良らを万家嶺へ案内させました。一年前、日本軍第106師団が万家嶺に侵入、中国第九戦区司令の薛岳は10万以上の大軍を動員して日本軍第106師団を包囲殲滅、日本軍に甚大な打撃を与えました。万家嶺は、日本軍によって「血嶺」、「傷心嶺」と呼ばれていました。

王啓明と師長の唐永良は、戦後初めて万家嶺に入った中国軍人でした。王啓明は生涯忘れられない光景を目撃しました。万家嶺周辺の山腹は至る所に散兵壕と屍骨が散乱し、ぼろぼろの革靴、ゴム靴がいたるところに捨てられていました。張古山から下りると、畢嘰嶺に到着。この山にはさらに多くの屍骨、頭蓋骨、ヘルメット、革靴、ゴム靴、軍用品が散乱していました。現場に残された毒ガスボンベ、砲弾箱、銃剣などの遺留品から、日本軍の死者が多かったことが伺えました。
墩上郭、馬鞍山から見ると、東の大金山、小金山、そして西の羊角尖は、当時敵味方双方が激しく争奪した陣地でした。当時、日本軍第106師団は数個大隊を派遣し、この一帯の山地を突破し、白槎、張公渡へ直進、中国守備軍第32軍の退路を断とうとしましたが、逆にこの一帯の山頂の北側のごく狭い地域に包囲され、甚大な損害を受け、ほぼ全滅しました。麒麟峰を奪取する戦闘では、第32軍の鄭克己団長、張樹衡副団長、秦闊沢営長が戦死、兵士の死傷者はさらに甚大でした。

王啓明らは畢嘰嶺を下り、小川沿いに蕭炉蘇を経て万家嶺主陣地へ。沿道には多くの木札があり、日本軍兵士の名前が書かれていました。また、地面には大量の屍骨、ヘルメット、銃剣、水筒、雨具、砲弾箱、砲弾の殻などの軍用廃棄物が散乱していました。万家嶺は低い丘陵地帯で、中国守備軍第4軍は当時大金山、小金山を占領し、高所から日本軍を攻撃していました。そのため、大小金山の争奪は非常に激しく、日本軍の死傷者も最も多かったのです。
万家嶺下に住む70歳以上の老人は王啓明らに、昨年10月、国軍がこの地で何千何万もの日本兵を打ち殺し、中には彼の茅葺屋根で食事をした日本兵もいたと語りました。当時、日本兵は周囲の山頂にいる中国兵に包囲され、戦闘は非常に激しく行われました。山の竹林、灌木地帯は至る所に敵味方双方の兵士が打ち殺されていました。日本軍は当時慌てて逃走したため、これらの遺体を運び去る暇がなかったのです。

老人の案内で、王啓明らは万家嶺の谷間で大量の日本兵の遺骸を発見しました。当時の光景は非常に印象的で、積み重なった日本軍の骨の下には高さ30センチメートル以上の蛹の殻が積み重なっており、日本軍の死傷者の多さが伺えました。万家嶺下の水田には、数十匹の軍馬の骨が整然と並んでおり、馬の口には轡が含められ、鞍、鐙の鉄部分はすでに錆びついていました。
山中の灌木地帯には、日本軍が捨てたヘルメット、靴が山のように積み重なり、雨水に浸かって白く色褪せた日本軍の軍服が万家嶺の山の灌木地帯や木の枝に引っかかり、まるで旗のように見えました。王啓明らは谷間で、日本軍が捨てた銃や折れた銃剣を発見しました。

老人によると、万家嶺戦役の後、日本軍第106師団は300人以上を万家嶺に派遣し、招魂祭を行いました。日本軍はここに一週間滞在し、万家嶺とその周辺の山の木、竹を多く切り倒し、日本軍戦死者の場所に墓標を立てました。万家嶺全体が様々な種類の札で埋め尽くされ、まるで木札の海のようでした。最大の木札には「噫噫皇軍陣歿将士之碑」と書かれ、また別の大きな木札には「瀬川部隊奮戦之地」と書かれていました。
日本軍は一週間滞在した後、万家嶺を離れ、周辺の村人たちは我先にと山に押し寄せ、ヘルメット、銃、靴、銃剣などを拾い集めました。当時、村人たちは百個以上の壊れたヘルメットを木札にかぶせており、それは非常に興味深い光景でした。当時、あたり一面に薬莢、銃剣の鞘が散乱しており、ある村人が拾った銃剣の鞘には16個の弾痕が開いており、当時の戦闘の激しさを物語っていました。
正午頃、王啓明と警衛連の兵士たちは手分けして、万家嶺の山の上から下まで、そして付近の墓を一つ一つ点検しました。日本軍の墓と遺骨は少なくとも3千体あり、畢嘰街、張鼓山の日本軍の墓と遺骸は含まれていません。万家嶺の点検を終えた王啓明らは万家嶺を下り、谷沿いに小川を渡り、雷鳴鼓劉付近に到着しました。

雷鳴鼓劉村東側の水田には、整然と日本軍の戦死した馬が並んでおり、万家嶺陣地と同様に、死んだ馬には鞍、鉄環が括り付けられていました。水田付近の大きな窪地には、死んだ馬が五、六百匹おり、王啓明らは77個の馬の頭蓋骨を積み上げ、唐師長はこれらの馬の頭蓋骨の写真を撮りました。
山の中腹には、「皇軍愛馬之碑」と「瀬川部隊陣歿愛馬之碑」と書かれた二つの大きな木札が立っていました。雷鳴鼓劉村の大きな木には、日本軍が樹皮を削り、空白部分を作り、そこに「雷鳴鼓劉激戦之地」という八文字を書き、その隣に「昭和十三年十月竹内部隊宿此樹下」と小さく書かれていました。当時、王啓明らは大まかに統計を取りましたが、雷鳴鼓劉村、万家嶺、畢嘰街(背溪街)一帯の戦場では、日本軍の骸骨は少なくとも6千体以上、馬の骨は少なくとも1千体以上ありました。

万家嶺激戦時、日本軍第106師団師団長の松浦淳六郎中将は、雷鳴鼓劉村の農民、劉茂良の家の古い家に隠れて日本軍を指揮し、最後の抵抗を試みました。雷鳴鼓劉村から畢嘰街(背溪街)以西、以南の山地は日本軍の一旅団、東側は日本軍青木旅団、北側は師団予備隊第一二三連隊と師団直属部隊でした。砲兵は雷鳴鼓劉村付近に、輜重兵の馬と山砲兵の馬は鼓村付近の窪地に隠蔽されていました。
激戦が始まると、日本軍は南田舗、雷鳴鼓劉、潘家の三つの村付近の周囲約4平方キロメートル以内に包囲され、圧縮されました。日本軍は空から将校の支援を受け、また援軍を次々と増援したため、最終的に日本軍は万家嶺から脱出しました。日本軍第106師団を全滅させることができず、松浦淳六郎を捕虜にできなかったことが、この戦いにおける最大の遺憾となりました。万家嶺での出来事は王啓明に深い印象を与え、彼は日記に万家嶺大捷を「万家嶺は日本軍の煉獄であり、ここは日本軍の墓場である」と評しました。

万家嶺大捷は、平型関、台児荘と並び、抗日三大捷と称されています。日本軍第106師団は万家嶺でほぼ全滅し、万家嶺は中国軍人が抗日殺敵を象徴する重要な場所となりました。王啓明団長が目撃した万家嶺のすべての光景は、今読んでも依然として心を奮い立たせます。
【本文は稗史候が抗戦資料、回顧録を収集、整理、執筆したものです。誤りや不備な点があれば、読者の皆様にご指摘いただければ幸いです】